心理学でストレスコントロール―不安定な心の心理状態を客観的に知る方法
私たちは日々職場や学校でのストレス、対人関係、勉強、恋愛、家族などさまざまな心の問題や葛藤を抱えて生きています。これらの問題に対処するには心の働きや感情、行動、欲求などを客観的に理解し、納得することで問題を解決することができます。心理学の知識があると自分や相手の心を正しく受け取ることができ、余計なストレスから解放されます。
心理学とは
心理学とは非常に広範囲な学問で、人の行動とその原因を探る科学的な研究と定義されています。心理学は外から見たり観察できたりする行動と、考えや感情など外から観察できない内面のことに焦点があてられます。 例えば以下のものが心理学と関わりがあると言われています。
・大脳の働きと意識や行動
・攻撃の原因や遺伝子
・特性や行動と生育環境
・子育て
・睡眠と夢
・精神病と行動障害
・薬と脳の機能
・超感覚的知覚(ESP)
・中毒(依存症)と治療
・人格
・知能
・騒音や公害などが与える影響
・ストレスと死因
心理学は非常に広範囲で複雑です。さまざまな観点から仮説が立てられて結果を比較し、データから法則性を導き出します。人間には個人差があるのでどのような場合でも法則が必ず当てはまるわけではありません。しかし、心理学によって人間の行動を理解し、自分や相手の心を正しく受け取れることができれば対人関係が好転し、もっと人間は健やかに感情をコントロールして生きていくことができるのです。
心理学のあゆみ
心理学の起源
心理学の起源は古代ギリシャです。語源は心=psycheと学=logosから成り立っています。心についての考察は古くからあり、古代ギリシャの哲学者たちがその源流だと言われています。医学の祖であるヒポクラテスは体を構成する4体液説を唱えました。病気は4種類の体液に変化が生じたものであると提唱しました。
この説に影響を受けたガレノスは、これらに対応する4つの気質を以下のように分類しました。
「多血質」「粘液質」「憂鬱質」「胆汁質」
・多血質 陽気な性格
・粘液質 鈍重な性格
・憂鬱質 うっとうしい性格
・胆汁質 怒りっぽい性格
この考えは後に心理学の「性格類型」に大きな影響を与えました。この他にもプラトンが生得説、アリストテレスが経験説、アウグスティヌスが物心二元論など哲学的なアプローチで考察していきました。
フロイトの精神分析学
心理学と言えばフロイトが有名です。彼はウィーン大学で生理学と心理学を学び、精神科医として患者の治療にあたっていました。彼は遺伝傾向と環境についての考えに影響を受けた一方で、人の行動と複雑な心理についても深く注目していました。
フロイトは意識できるのは心のごく一部であり大部分は無意識の領域で、無意識の世界が人間を動かしていると説きました。
・無意識は人間の本能、欲動の中心(エス、抑圧)
・意識領域は望ましい自分、理性として働く(自我)
・大部分が無意識の領域、必要に応じて意識できる(前意識)
・親によって躾られる間に内面規範となった(超自我)
フロイトはヒステリー研究のほか、人間の行動の根源には性的色彩やエネルギーを帯びていると考えていました。アドラー心理学で有名なアルフレッド・アドラーはフロイトに共感していたものの、性欲というよりも優越感や承認欲求など個人心理学理論を打ち立てました。

嫌われる勇気
日本でもアドラー心理学の教えを説いた岸見一郎・古賀史健著の『嫌われる勇気』がベストセラーになりました。心理学に興味のある私も読みましたが、これまでの常識を覆させられる内容でした。
心理学といえばフロイト、ユング、そしてアドラーが三大巨頭として取り上げられます。フロイトは意識や無意識(抑圧)、ユングはシンクロニシティ、ペルソナ、夢判断。アドラーはもっと私たちに身近な人間理解の真理として私たちの心にアプローチしていると感じます。
フロイトは成長とともに本能をコントロールしながら自我を形成し、良心は超自我として働き、罪や葛藤、自我と向き合ってぶつかりあいながら生きていると説きました。そして人間には過去に体験したことや経験を意識的に思い出したりする前意識があり、辛い過去や経験は無意識の領域に追いやられ、抑圧されます。
フロイトはこういった心の不安や恐怖の源流をトラウマや因果律などの「原因論」としましたが、アドラーは主観的な思い込みと提唱しました。 つまり、アドラーは不安や恐怖は自らの意志の力で過去のしがらみや感情を作り上げていると考えたのです。
例えば、自分が変わりたいと思っているとします。しかしアドラーの教えでは自分が変わらないという決心をしている、というのです。自分の人生を決めるのは自分。過去ではなく「今、ここに生きている自分」だと。
私の個人的な考えですが、やはりトラウマはあると感じます。しかし、フロイトのように過去の辛い感情や経験をトラウマとして処理してしまえば過去のしがらみにずっと縛られ、前進することができなくなってしまいます。人間は辛くても前を向いて生きていかなければなりません。だからアドラーの「今、ここに生きている自分」が人生の舵を取るという考えは素晴らしいと思います。
人間は感情と欲求に支配されている
人間は感情の動物であると言われています。感情はある特定の精神状況を主観的にとらえたものであるため客観的にとらえることは大変難しいです。しかし、怒りや恐れなどは危険なものを避けるための準備であり、心拍数が上がったり鳥肌が立ったりして身体の反応や行動が伴います。
また、感情は欲求と密接な関係があります。例えば、空腹になって食欲が生じます。何かを食べて空腹が満たされると快の感情が生じますが、欲求が満たされないと不快の感情が生じます。欲求は食欲のほかにも睡眠、呼吸などのホメオタシスを保ち生存を維持するものから性的欲求、好奇心、人間関係の中で生じる攻撃や支配欲求などがあります。
【ふられた相手の悪口を言う心理】
相手に振られたとたん、掌返しをして相手の悪口を言ったりけなしたりする人がいます。これは相手に振られたことを認めたくないことから生じる行動です。心理学では「合理化」と言います。 イソップ物語のキツネは手に入らない届かないブドウを見て「どうせ酸っぱいにきまっている」と言いました。つまり、どうしても手の届かないブドウを目の前にしてストレスが溜まり欲求不満になっているのです。そこで動揺を隠すためにブドウの価値を落として自己防衛をしたのです。
【なかなか手に入らないものを欲しがる理由】
それではなぜ人間は手に入らないものを欲しがるのでしょうか。ギャンブルにのめり込む心理はめったに当たらないからなのです。ギャンブルをやめようと思っても「大当たり」が出るとその行為に熱心になってしまう、熱中してしまう。それは、たまに与えられる大当たりのご褒美がやめられない原因になるっているのです。
健全な努力と成長
これまで述べてきたように人間はさまざまな感情や複雑な心理、欲求を持っています。他人と比較して落ち込んだり、優越感を抱いたり。人間のすべての悩みは対人関係であるとアドラーは説いています。人間には普遍的な欲求(優越性の追求)があり「向上したい」という志や目標、目的があります。そのため他人の幸せを祝福するよりも嫉妬や妬み、焦燥感が出てしまうのです。
ここで問題なのは、他人と自分を切り離して考えられない主観的な劣等感なのです。自慢する人は自らの劣等コンプレックスを言葉や態度で表明しているだけで、「あの人さえいなければ自分は有能で価値がある」と言外に暗示しています。だから人の悪口を言う人は、自らのコンプレックスや劣等感をさらけ出しているということがわかります。つまり、他者より有意に立つことで特別な存在であろうとしているのです。
主観的な思い込み、誤った考え方、劣等感を払拭しないと、人は常に誰かと競争し勝ち続けなければなりません。しかしそれは不可能です。アドラー心理学は他者を変えるのではなく自分が変わるための心理学です。 対人関係の悩みは他者との比較から始まります。他者と自分を切り離す、他者のことに干渉しない、自分の課題にも干渉させないことが大切です。
多くの人は安易に他者を批判したり攻撃したりして自分の優越性を追求しようとします。これは不健全な努力です。問題行動に走るのは注目されたい、特別な存在でありたいという欲求から生じます。 何らかの結果を残すには努力が必要です。この努力ができない、しない、回避しようとするからおかしくなるのです。
しかし、皆が特別な存在である必要があるでしょうか。健全な努力や普通であることの勇気が大切であると書籍には書かれています。人生はシンプルであり、複雑にしているのは自分なのです。
まとめ
心理学、とくにアドラー心理学に焦点を当てて人間の感情や欲求、劣等感、優越性の追求などに触れました。また、書籍『嫌われる勇気』に書かれている内容も一部ご紹介しました。幸せになるためには書籍タイトルにある「嫌われる勇気」も含まれるそうです。幸せになるには他者の評価を気にせず、自分の生き方を貫いて自由になること。私も心がけて実践したいと思います。
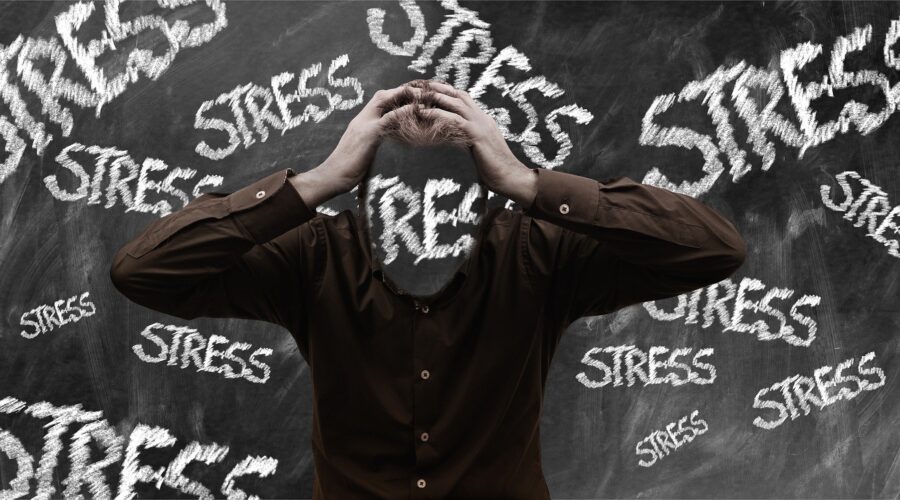
コメントを残す